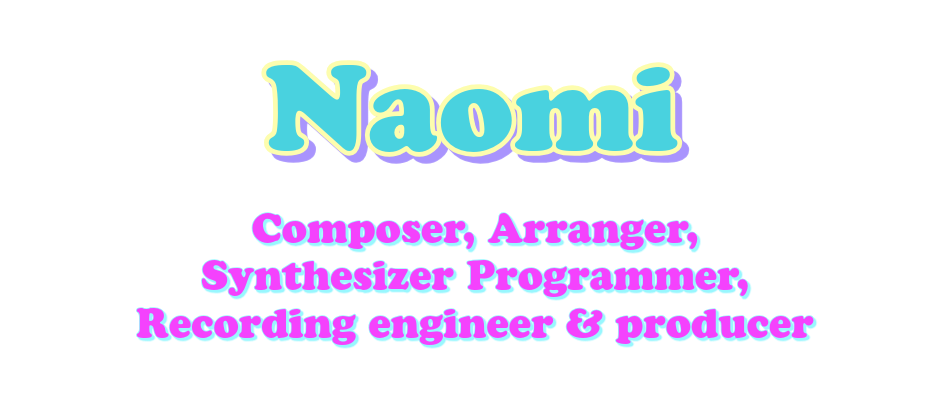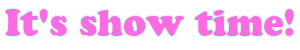Naomiについて
|
私はDIY (do-it-yourself) ミュージシャンです。 作編曲からレコーディングまでだけでなく、企画、宣伝、ジョークの考案まで すべて一人で行っています。 もちろん、イラストも私が描いています。 Naomi ワールドをどうぞお楽しみください! |
 |
(⇧ 本人がシャイなため、彼女が代わりに親善大使を頑張ってくれています。)
↑NaomiについてのFAQ↑
~こんな感じで作っています~
1.作曲
ピアノの鍵盤を触りながら考えることが多いです。
通常はどのようなテーマで作るか決めてから作業をしますが、しっくりくるものに辿り着くのに5分とかからなかったこともあれば、1か月悩みに悩んだこともあります。
メロディや和音、曲の持つリズム感などに十分納得がいく状態になると、おのずと次の作業である編曲の大まかな形が見えてきます。
2.編曲
珍しいかもしれませんが、何か特定の楽器のために曲を書く時以外は、音を鳴らさずに行うことが多いです。
作曲が終わった段階でどのような編成(ドラムが入るとかたくさんの種類の音を使うとか…)にするか大まかに決まっているので、頭の中で音を思い描きながら、黙々と五線譜に音符を書いていきます。
たまにドラムが入る曲の場合に、机をトントンたたいてリズムを確認することがありますが、恥ずかしいので人に見られないように気をつけています(笑)
編曲の作業と並行してどのようなシンセサイザーの音色(おんしょく)
3.打ち込み
ここからはパソコンに電源を入れ、音楽制作ソフトを使用して音楽を形にしていく作業になります。
コンピューター上で音楽を演奏するには、すべての音を一つひとつ、どの タイミング・長さ・強さ・音色 で鳴らしたいのか、などをコンピューターに命じる必要があります。この ”打ち込み” とは、コンピューターにどのように演奏してもらうかの "データを作る作業" に他ならないのですが、この一見複雑な作業を直感的かつ音楽的にできるように助けてくれるのが、音楽制作ソフトです。
音楽制作ソフトは一般的にDAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれていますが、これはDAWがあれば、作編曲した曲をレコーディングして、みなさんに届ける形にまで持っていけるからで、私が一人で音楽制作が可能なのは、このDAWによるところが大きいです。技術者、開発者のみなさんに深く感謝しています。
DAWには鍵盤を弾きながら実際に演奏するのに近い感覚でデータを入力できる機能がありますが、私の場合はひたすらパソコンのマウスとキーボードを用いて、文章をパソコンで入力するのに近い感覚でデータの入力を行っています。
データの入力作業と並行して、コンピューター上で動作するシンセサイザー、”ソフトウェア・シンセサイザー”を起動します。(私はソフト・シンセと呼んでいます。)
Game Pop、 Monochrome Night で使われているすべての音が、ソフト・シンセの音色です。
聴いていただくと、実際に存在する楽器の音を模倣したもの、もしくは録音したものから、シンセサイザー特有の電子音まで、さまざまなバリエーションの音色があることがお分かりいただけるかと存じます!
そして、これらの音色は曲想に応じて調節が可能で、音楽的に大きく貢献してくれています。
DAWと同様、シンセサイザーの技術者、開発者のみなさんに深く感謝しています。
4.レコーディング(ミキシング)
打ち込みを終えた後はレコーディングの準備に入ります。
レコーディングとは文字通り、音楽をハードディスクなどのメディアに録音することです。しかし、レコーディングはミキシングとも呼ばれます。
それはなぜかというと、レコーディングの作業はたくさんのトラックや音を文字通り "mix" する作業だからです。
トラックとは録音物の最小単位で、レコーディングでは様々な楽器が使われていても、各楽器の音を1つずつそれぞれのトラックに録音を行ってから、最後にすべての音を1つにします。(もちろん、一度にすべての音を録音することもクラシックのコンサートなどで行われています。)
"Game Nostalgia" を例にとってご説明します。
"Game Nostalgia"は5つのトラックで構成されています。
(1)メロディパート のトラック
(2)和音パート・左側のスピーカーからのみ音が鳴るトラック
(3)和音パート・右側のスピーカーからのみ音が鳴るトラック
(4)リズムパート のトラック
(5)ベースパート のトラック
レコーディング作業ではこれらの5つのトラックを、1つのステレオトラックにまとめるのです。トラック数が5つから1つへと減ることから、この作業は "トラックダウン" や "ミックスダウン" とも呼ばれます。 他の曲だと"Space Shooter"ではもとは124個トラックがあったものを1つにまとめています。
また、上記の(2),(3)についてですが、"パンニング"という作業もレコーディングでは行われます。これは、トラックがスピーカーのどのあたりの位置から鳴るのか指定することなのですが、録音物のステレオ感を生み出すことと密接な関係があります。
ミキシングで最も重要なことは、音のバランスを考慮することです。バランスは音楽の印象を左右します。
ですからミキシングの基礎はけっこうシンプルで、おのおののトラックの相対的な音量のバランスをとることにあります。
他に行うこととしては、エフェクターを使います。エフェクターにはリバーブ(音に残響を加える)、ディレイ(音に山びこ効果を与える)、イコライザー(音の特定の周波数を強めたり弱めたりする)などがあります。これらもトラックごとに使い分けて用います。
これらのエフェクターは響きを豊かにしてくれるので、私の場合に限らず多くのレコーディングで用いられていることと存じます。
5.マスタリング
マスタリングとは、もともと工場でLPレコードやCDをプレスするためのマスターを作成する作業のことを指すので、この項の作業は厳密にはプリマスタリングと呼ばれることになります。
ただし、ここではプリマスタリングのことを便宜上マスタリングと呼びます。
マスタリング作業においては、曲ごとの聴感レベル(耳で実際聴いてみた時の音量の感じ)をそろえたり、イコライザーによる音質の調整、曲が終わってから次の曲が始まるまでの長さの調整などを行います。
また、音圧レベルを上げることもよく行われています。実は、"Game Pop"においてはぎりぎりまで音圧を上げるかどうかで悩みました。
しかし、最終的には音圧を上げるのは保留にしました。というのも、音圧を上げることにはリスクもあるからです。
前述のレコーディング作業では音の奥行きを大切にしてミックスダウンを行いましたが、音圧レベルを上げようとすると、どうしても、奥行きを全く変えずに音圧だけを上げるのは難しくなりますし、音圧を上げると意図しない音の歪みが生じることがあります。
私としては、音の奥行きは音楽における最も重要な要素の一つだと考えております。ボリュームを適宜調節していただいて、音楽をお楽しみいただけたら幸いです!
6.リリースの準備
配信ストアさんとの契約前に、ビジネスとして重要な手続きを2つ行います。
(1)作品届の提出:作品を適切に管理してもらうためにJASRACさんに提出します。国際的にも管理していただける仕組みになっています。
(2)ISRCの申請:ISRCとはInternational Sound Recording Cordの略で、レコーディングしたものを識別したり、管理するのに役立つコードで す。一つのレコーディングに対して間違いなく一つのISRCコードを割り当てる義務があります。レコード協会さんに申請して発行してもらいます。
これらの手続きが終わると、契約の準備に入ります。たくさんの配信ストアさんと円滑に契約ができるように、契約代行業者さんにお手伝いいただいています。
ここまでお読みいただきありがとうございました!ざっくりと制作からリリースまでご説明させていただきました。
実際の作業は私ひとりで行っているものの、信頼できる機関、会社、そしてみなさんの手厚いサポートにより、音楽制作が成り立っていることがお分かりいただけたことと存じます!
うまく表現できていない部分もあるかと思うので、今後も改善していきたいです。
それでは私の曲をお楽しみください!